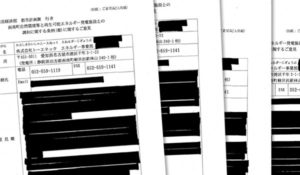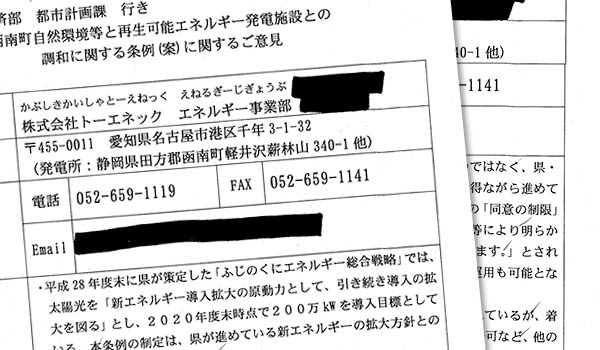
何ら法的根拠なく「条例は適用できない」と言いつづける仁科町長。その言い分は、事業者が提出したパブリックコメントの内容そのものだった。
考える会が函南町に情報公開で求めたトーエネックのパブリックコメントの内容は、前編でご覧いただいた全て黒塗りのものだった。
→ 前編
これに抗議すると今度はその情報公開まで2ヶ月の公開延長となった。
更にそれに抗議することでやっと以下のとおり全てのコメントが公開された。
一体、函南町は何を隠したかったのか?
まずは、ご自身の目でじっくりとお読みいただきたい。
•平成28年度末に県が策定した「ふじのくにエネルギー総合戦略」では、太陽光を「新エネルギー導入拡大の原動力として、引き続き導入の拡大を図る」とし、2020年度末時点で200万kwを導入目標としている。本条例の制定は、県が進めている新エネルギーの拡大方針との間に不一致があるのでないか。
•平成30年12月定例会で町長が、「住民とのトラブルや景観上のことや、それから第二次災害の誘発をする、そういうことは必ず避けていかなきゃならないというのは言うまでもない話なんです。そういうものを、今ある土地利用対策部会であるとか県の森林法、林地許可のものによるとか、そういうもので規制をしていこう」と述べているとおり、森林法等の既存法令および静岡県太陽光発電設備の適正導入に向けたガイドライン検討会が策定したモデルガイドラインに従って事業を実施すれば、条例にて企図している目的は達成できるはずであり、あらためて条例を制定する意味が不明瞭である。
・素案の「稼働状況等に関する報告」において「稼動状況及び使用済み設備の撤去、処分費用の積み立て状況について、翌年度の4月末までに町長に報告しなければならないこととします。」とあるが、事業者が設備を適切に維持管理することはともかくとして、太陽光の稼動状況等についてまで報告させる意味が不明瞭である。
・事業規模等の大雑把な分類によって一律に規制するのではなく、県・市・町と防災・排水問題を協議し、地元住民の理解を得ながら進めている事業に対しては同意すべきと考える。この点素案の「同意の制限」においては、「ただし、事業地及びその周辺区域の状況等により明らかに支障がないと判断される場合は同意できるものとします。」とされているが、このままでは、行政の裁量が広く恣意的な運用も可能となるので、同意の判断基準を明らかにすべきである。
・素案では、着手の60日前に届出し、同意することとされているが、着手の定義がない。着手とは、「森林法における林地開発許可など、他の法令において必要とされている許認可に関し、法令上の図書を関係行政庁が受理していること」等と具体的に定義して明確にすべきである。
・届け出を受けての同意の成否が判明するまでの期間が明示されておらず、いわゆる「握りつぶし」のような状態が発生しないが危惧される。
同意についての応答期間を明示すべきである。
・今回パブリックコメントに付された素案の審議過程に関しては、平成30年12月までの定例会資料しか公表されておらずく平成31年3月の定例会資料が公表されていないため、審議の最新情報が不明である。パプリックコメントを実施するのであれば、最新情報について公開することは必須である。
・素案には経過措置の記載もなく、具体的案件への適用の有無等、事業者が事業の実現可能性を判断するために必要な情報が不十分である。このような素案を元にパブリックコメントを求め、条例制定をするという手続きは不適当であり、条例の詳細が決まった後、再度パプリックコメントを実施すべきである。素案では事業者は予測可能性が見通せない。
・抑制区域の範囲が広すぎ、基準が不明確でないか。森林資源や自然災害予防、生活環境の保全、景観保全、文化遺産保全と極めて広汎で抽象的な区域となっており、投網を掛けるような規制になるおそれがある。森林法や砂防法など個別法律との整合性も明らかでない。
・素案の施行期日にて「この条例は相当の周知期間を設け、令和元年10月1日から施行する」とあるが、周知期間とは公布から施行までの期間のことか。令和元年10月1日の施行を前提とすれば、現時点でパブリックコメントを実施しているようでは相当の周知期間が確保できないのではないか。
・既に進行している事業については、条例による規制を予測せずに実施しているため、事業者の予測可能性と既に投下した資本に配慮すべきであり、基本的には条例の適用対象とすべきではない。具体的には、既に着手している案件には適用されるべきではなく、この着手についても、「森林法における林地開発許可など、他の法令において必要とされている許認可に関し、法令上の図書を関係行政庁が受理していること」等とすべきである。なぜなら、太陽光の大型案件等は、林地開発許可、環境アセスメント等について長期間を必要とすることが多く、着工が遅くなる可能性があるからである。よって、「着手」の定義を明確にしたうえ、相応の経過措置を設けるべきである。
① トーエネックが町に提出したパブリックコメント (3件)
② トーエネックが町に提出したパブリックコメント (3件)
③ トーエネックが町に提出したパブリックコメント (3件)
④ トーエネックが町に提出したパブリックコメント (2件)
仁科町長が繰り返し発言してきた「許認可に関わる申請を何かひとつしただけでもう事業開始と解釈」し、それを根拠として「遡及問題がある」という摩訶不思議な理屈は、正に事業者の言い分そのものだったのだ。
住民の安全安心を守るという条例の目的を無視し、他の市町には無い特殊な解釈で事業者に忖度した運用を行う理由は何なのだろうか?
関連記事
→ やはり函南町だけ特殊だった条例解釈
自らの疑惑を晴らすための会議を欠席し、それに関わる警察の捜査が進むと2度にもわたり不可解な職員の処分を繰り返し、強引に事件決着を急ぐ理由は何なのか?
関連記事
→ なぜ仁科町長は欠席したのか?
→ またしても繰り返された不可解な処分